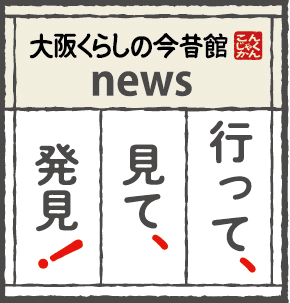95
95
会話を誘い出す天神祭ーおもてなしの仕掛けー

|
大阪天満宮文化研究所所長 高島 幸次 |
平安中期の天暦三年(949)に大阪天満宮が創祀されると、その翌々年には天神祭が始まりました。とはいっても、当初の天神祭は大川沿いのわずかな漁民たちが奉仕する小さな祭礼でした。
その後、地域の開発に伴って拡大し、江戸中期の元禄期(1700年頃)には、大阪の町の隆盛に呼応するかのように、日本三大祭の一つに発展します。あの井原西鶴も、「天満の舟祭りが見ゆるこそ幸いなれ」(『世間胸算用』1692年)と記すほどです。
この大発展の要因の一つに、見物客と地元町人との会話を誘発する仕掛けがありました。それは、会話好きな大阪町人らしい「おもてなし」の具現化とも言えます。以下、その具体例を「お祭り提灯」「御迎え人形」「造り物」に見ていきましょう。
1.お祭り提灯の場合
「お祭り提灯」は、現代の祭礼でもよく見かけますが、その多くは読みやすい字体で「御神燈」や「献燈」などと印刷された規格品です。
しかし、江戸時代の天神祭では、町内ごとに提灯に記すオリジナルな文字が定められていました。しかも、その文字は、儒教の経典などから採られた難しい語彙や、謎々のような語句で、しかも、読みにくい篆書(てんしょ)体や隷書(れいしょ)体で墨書されていました。読むのも一苦労、たとえ読めても意味が解らないという厄介な代物だったのです。
と説明しますと、「どこが、おもてなしやねん!」とつっこまれそうですが、もう少し我慢ください。ここからがキモなんですから。

OAPタワーでは、天満宮の氏地各町の提灯を復元し、毎年七月に一階エントランスで展示しています。
【写真1】は、市之側(天神橋北詰から、西方の太平橋までの浜通り)に掲げられた提灯です。こんな難読の文字では、見物客は「なんて読むんやろ?」と気になって仕方がない。
ちょうど、軒下の床几(しょうぎ)で寛いでいるお年寄がいたので、「すんません、これ、なんて書いてますねん?」と聞けば、お年寄は待ってましたとばかりに、「あぁ、これはね、表は〈えいしゃく〉、裏は〈そいん〉ですねん」と教えてくれる。
重ねて「どういう漢字?」と問えば、お年寄はかねて用意の『詩経』を取り出し、「ほら、ここに載ってまっしゃろ」と「君子萬年(くんしばんねん) 永錫祚胤(えいしゃくそいん)」の箇所を指さすが、これまた難しい。
お年寄は「君子萬年、永く祚胤を錫(たま)わん、と読みまんねん。祚は〈福祿〉、胤は〈子孫〉のことでっさかい、君子(徳の高い人)の長寿を祈り、長く子孫の繁栄を願うような意味ですわ」と教えてくれる。
「よう、そんな難しいこと知ってはりまんなぁ」「死んだ親父がね、ここに座ってたら、必ず誰かが聞いてくるから覚えとけちゅうて、教えてくれたんですわ」と嬉しそう。ここまでくれば、二人は旧来の知人のよう、どんどん会話が広がります。
そうなんです。この難読文字は、他所から来た祭り見物の客が思わず尋ねたくなるための仕掛けだったのです。見物客との会話を誘発し、そこからおもてなしが始まるのです。
樽屋町(北区西天満三丁目)に移動すれば、提灯には「尊木」と記されています。これは誰でも読める墨書なのですが、意味不明。そこで「どんな意味ですか?」と問えば、「あぁ、これは町名の〈樽〉の字を偏と旁(つくり)に別けただけですねん」「おもろいなぁ!、どんな難しい漢文から採ったんやろと思いましたがな」と、ここでも会話が弾みます。
2.御迎え人形の場合
天神祭の本宮、七月二十五日の夕刻には船渡御が斎行されます。現在は天神橋から上流の飛翔橋に遡航しますが、戦前までは天満宮の地先から下流の御旅所(西区の雑喉場、のち戎島。現在は千代崎)に航行していました。
そのころ、御旅所周辺の町々では船渡御を迎えるために御迎え船を仕立て、その船上には豪華絢爛の風流人形を飾ったのです。これが「御迎え人形」です。人形は、御迎え船に飾る数日前から御旅所周辺の店先などでも披露されました。
人形の数は、江戸後期の最盛期には50体を超え、そのキャラクターは当時人気の文楽・歌舞伎から採られました。例えば、木津川町(西区千代崎一丁目)に飾られた「羽柴秀吉」は、歴史上の人物というよりは、芝居の『祇園祭礼信仰記』に登場する「此下東吉(このしたとうきち)(のち真柴久吉(ましばひさよし))」を模したものでした。
なかには、人間以外の人形?もありました。戎島町(西区川口一丁目・本田一丁目)に飾られた「源九郎狐」を見れば、誰もが『義経千本桜』での大活躍を思い浮かべたのです。芝居好きの大人が、子どもたちに「この狐は、義経に仕えた佐藤忠信に化けて、親狐の皮を張った〈初音の鼓〉を持つ静御前を護ったんやで」と教える姿が目に浮かびます。

人形細工人の大江忠兵衛の作。忠兵衛が作った生き人形に菊細工を施したのが「菊人形」なのです。
江之子島東之町(西区江之子島一・二丁目、立売堀六丁目)には、「鬼若丸」と【写真2】の「関羽」の人形が立てられました。現代では「鬼若丸」を知る人も少なくなりましたが、『鬼一法眼三略巻(きいちほうげんさんりゃくのまき)』に登場する武蔵坊弁慶の幼名なのです。
「関羽」については、『三国志』の登場人物、として有名ですが、この人形は芝居『閏月仁景清(うるうづきににんかげきよ)』で活躍する関羽なのです。芝居を観て来たばかりの町人が、遠来の見物客に「この関羽が鬚をしごいてるのは〈関羽見得(みえ)〉ちゅうてな・・・」と得意げに講釈する姿を想像してしまいます。
そうなんです。先のお祭り提灯と同じく、御迎え人形も、人形をこしらえた町の人々が、見物客との会話を引き出すための大切なツールだったのです。元禄以降の大阪町人の芝居好きを考えれば、これほど嬉しいおもてなしの仕掛けはなかったでしょう。
3.造り物の場合
江戸時代の大阪では、神社の「正遷宮」や、祭礼に「造り物」を飾って祝意を表す習慣が
ありました。造り物とは、ありふれた日常品の風合い(手触りや見た感じ)に着目し、別のものに見立てて(他のものになぞらえて)作ったものをいいます。菊花を着物の模様に見立てた「菊人形」も造り物の一種です。
奇抜な意外性のある材料で意表をつき、その造形の工夫や巧みさで驚かせるのです。アイデアと技術の勝負だと言って良いでしょう。
天神祭の造り物といえば、「蜆(しじみ)の藤棚」と紙製の「牡丹の花壇」が定番でした。『天満宮御神事 御迎船人形図会』(1846年)には次のように説明されています。
| 天神橋北詰より東へ市場の間、蜆の貝殻をもって藤の花を造り、数丁、藤の棚をしつらえ、同西へ市之側商家の屋根ごとに牡丹の花壇を造る。 |
天神橋北詰の東方に伸びる天満青物市場の店々の軒下には、蜆の貝殻で造った藤棚が吊るされ、西方の商家の屋根並みには、ペーパークラフトの牡丹の花壇が設けられていたのです。

毎年の天神祭には、参集殿前に「御迎え人形」とともに飾られます。
実は、現在の天神祭でも、ボランティアガイド「天満天神御伽衆」が、この蜆の藤棚を再現して、天満宮境内に飾っています(【写真3】)。数年前の天神祭に、ある参拝者が御伽衆に「こんな真夏に藤の花が咲くのはおかしいと思うたんや」と話しかけたことがありました。これは制作者にとってはシメシメの反応なのです。誰かに言いたくなる驚き、それが造り物の真骨頂なのですから。
造り物は、その風合いの相似性が高く、造形が巧みであればあるほど、元の材料を感じさせないものです。優れた造り物は、説明されて初めて、そのアイデアと技術に脱帽するのです。そして、そこから会話が始まるのです。
青物市場の商人たちなら、「大川の蜆の貝殻は、内側がきれいな紫色をしてまっしゃろ、ほやから藤棚に見立てたんですわ」と得意げに説明したに違いない。造り物も会話を引き出すツールだったのです。
おわりに-大阪締めの場合-
お祭り提灯、御迎え人形、造り物を例として、それが地元町人と見物客との会話を誘い出す仕掛けだったことを紹介しました。
しかし、天神祭最大のおもてなしは「大阪締め」なのかもしれません。年に一度の神様のお出ましを祝って、「打ちまーしょ(チョン・チョン)、もぅひとつせ(チョン・チョン)、祝うて三度(チョチョン・チョン)」と手打ちを交わすのです。
現在の船渡御でも、船と船だけではなく、川岸や橋上の見物客と船上の氏子たちが、幾度となく大阪締めを交わします。
祭りの奉仕者と遠来の見物客が、これほど懸け隔てなく祝意を交わし合う祭礼を、私は他には知りません。天神祭は、まさに「おもてなしの祭礼」として発展してきたのです。
企画展「天神祭と都市の彩り」
2023年7月8日(土)〜2023年9月3日(日) のご案内

大阪で最大規模の都市祭礼である天神祭。菅原道真公を奉戴した御鳳輦(ごほうれん)が壮麗な渡御の行列とともに氏地を巡る様子は、古くから様々な書物の中で取り上げられており、江戸時代には色彩豊かな錦絵などを通じて、その賑わいが全国へと伝えられました。
元禄年間(1688年~1704年)以降になると、御旅所(おたびしょ)周辺の町々では当時人気を博していた歌舞伎や浄瑠璃の登場人物などを題材にした絢爛豪華な御迎え人形が作られるようになり、天神祭の演出は一層華やかさを増してゆきました。
江戸時代後期には50体を超えていたとされるこれらの人形は、祭りの日にあわせてそれぞれの町角で飾り立てられた後、氏子や崇敬者の仕立てた船に載せられ、船渡御の一行を奉迎する役割を担っていました。
本展では現存する御迎え人形(大阪天満宮蔵・大阪府指定有形民俗文化財)の一部をはじめ、大阪天満宮が所蔵する天神祭に関する貴重資料を公開します。また、今昔館のコレクションの中から納涼や夏祭りにちなんだ絵画作品などをあわせて展示し、円熟した町人文化のもとで育まれてきた都市祭礼の伝統とその魅力を紹介します。
企画展の詳細はこちらをご欄ください。